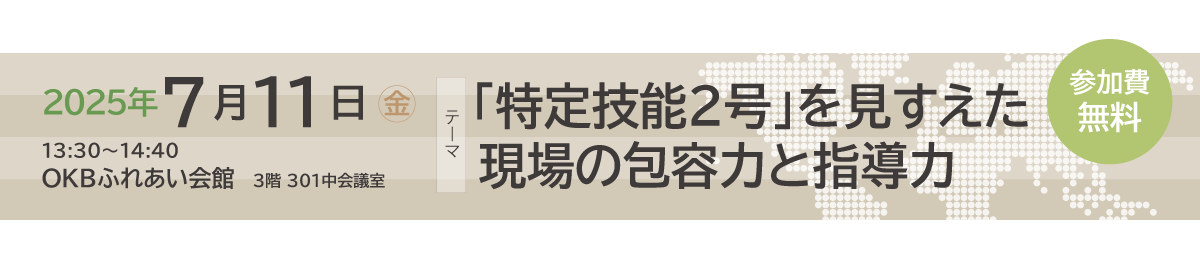不適切な事例集
私たちは、企業から「監理団体を変更したい」といったご相談を受けることがあります。そうしたご相談の中で、現在の監理団体の対応に関する実情を伺ううちに、一見「親切」に見える行為の中に、実は法令違反に該当するものが含まれていると判明することがあります。そして、そのような対応を当然のものとして、私たち新たな監理団体にも求めてくる事例も少なくありません。
また一方で、企業としては「定期的に訪問して助言をしてほしい」という正当な期待を抱いているにもかかわらず、監理団体がほとんど来訪せず、相談にも応じないといった不満の声も少なくありません。
監理団体としての信頼を損なう行為や、誤解されがちな対応について整理し、事例をもとに注意点をまとめました。以下に、こうした実態を踏まえ、監理団体として不適切とされる事例を紹介します。
~改善が必要な監理団体の特徴10選~
- 技能実習計画の内容を精査せず、現場確認を怠っている
時間数・作業工程・設備台数などを事前に確認せず、職種の齟齬を黙認する事例が見られます。 - 監査や訪問指導を実施せず、現場の実態を把握していない
給与明細書などの書類受領だけで、企業へ訪問をしていない事例が見られます。 - 日本に駐在する送出機関の通訳者のみが、監査を担っている
企業監査や実習生からの相談業務は、監理団体の役職員の責務であって通訳者は補助者に過ぎません。 - 技能実習日誌を監理団体の役職員が代筆している
本来企業の役職員が記録すべき内容を不適切に処理し、制度の実効性を損なっている事例が見られます。 - 企業の役割までを過剰に肩代わりしている
宿舎契約や生活指導までを請け負い、企業の責任感や自立的運用を弱めている事例が見られます。 - 実習生よりも企業側の都合を優先している
実習生の訴えや問題提起が軽視され、企業側の意向ばかりを尊重した運用になっています。 - 実習生の苦情や相談に適切に対応していない
実習生の相談を「不満」として片づけ、企業側の不信感を助長している事例が見られます。 - 日本語教育や生活支援を「企業任せ」にしている
監理団体が最低限の支援さえ講じず、実習生の安定した生活や快適な労働環境に配慮しない事例が見られます。 - 制度の仕組みを理解せず、専門性を有しないまま運用している
技能実習計画や講習の趣旨を理解しないまま、形だけの手続きで済ませている事例が見られます。 - 過度に安価な監理費で必要な監理支援を提供していない
コストを抑える一方で、定期訪問や相談対応など本来の監理業務を放棄している事例が見られます。
※ 上記は、本会会員メンバーの実体験をもとに整理したものであり、特定の団体を示すものではなく、団体名や件数などの具体的な集計を行ったものではありません。 また、本ページの内容に関する個別のお問い合わせや、特定団体の照会にはお応えいたしかねますので、あらかじめご了承ください。